誌
情
報
安楽病棟
出版社 : 集英社文庫 集英社 東京 2017
定 価 : 本体840 円 + 税
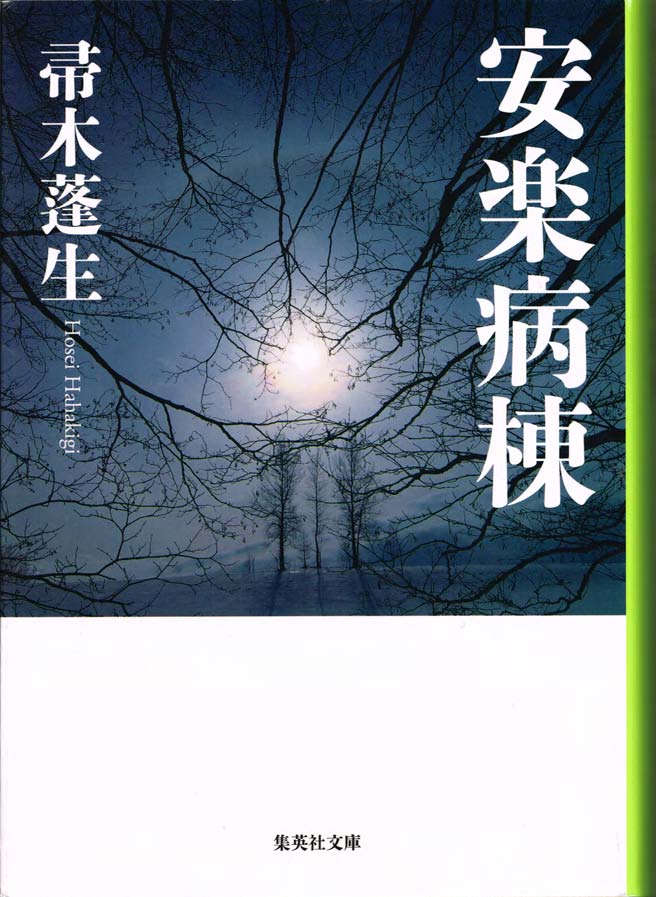
想
・
内
容
紹
介
この本を読んでいると、自分も年をとるとこうなるかも知れないとか、認知症の症状はこんなものがあるとか、患者レクレーションはこうすればよいとか、だいたい学習できるのではないかと思えるくらいあれこれ出てくる。文庫本で600ページの分厚さだ。
全部で三十のテーマに分けて書かれているが、ただ、日々の病棟活動の報告のような内容が多いから、それらを知識として得ようと思う人はノート片手に読むといい。私には教科書的な記述とさえ思えた。しかし、小説として読む分には平板で、患者が急変して死んでしまったとか、オランダの安楽死の考え方はこうだというような内容もあるのだが、全体として平板で退屈な本というのが第一印象であった。それで一気に読みきれず、最後まで読むのに何度も中断し読み終えるまでに結構な日時を要した。
そして、最終章の「動屍」を読んだ時、やっと本書のテーマに気づかされた。私にとってはずっと平板で退屈な本が、最後になって急展開という内容だ。作者の「作風」が恨めしくさえ思えた。タイトルの「安楽病棟」と「動屍」がやっと結びついたのだった。この最終章は、医師が巧妙な方法で患者を安楽死させたという主人公の告発文となっている。しかし、主人公も「安楽死」を完全否定はしていないような態度のように読んだ。
「屍」(かばね、しかばね)は、広辞苑によれば「死人のからだ」。従って、「動屍」をよめば「動く死人のからだ」となる。「死人の体が動く」とは、まだ「死人」ではなく「死んだも同然の人」を指しているようだ。
「安楽死」は高齢化社会の現実問題だ。医療を受ける側も、提供する側も、そしてそれを見守る家族の側も、「動屍」状態になったときにどう対応するか、難しい問題だ。医療は患者の命を救うことが使命だし、日本の医療制度の下では「安楽死」を提供することはできない。 「オランダ」という章ではオランダでの安楽死の考え方、「ワイン」という章では終末期医療の考え方が、最終章で主人公が「告発」した医師の口を通じて語られる。
「必要悪」という言葉があるが、「必要」かどうかはその時の社会の考え方に左右されると思う。ライ患者の収容所、障害者の強制不妊手術などは後に間違いだったと批判されている。だから、「安楽死=必要悪」とはやっぱりならないと思う。
いずれにしても、私の結論としては、本書はいろいろ勉強にはなるが退屈な本だ。